
「おじさんたちの聖域」といわれる横浜のディープ呑み屋街・野毛。ここ最近では気軽に呑めるお洒落な立ち呑み屋も増え、若者や女性ひとり客も増えてきた。この野毛を中心に「横濱で飲みたい人の読む肴」と銘打って酒場文化を紹介する人気雑誌『はま太郎』が、横浜の歴史と今をつなげる役割を果たしている。
『はま太郎』が誕生するまで
大学を卒業後、中規模出版社に勤めていた成田希さんは、仕事を通じて組版ソフトの使い方や流通の仕組みを覚え、思っていたよりも少人数で本がつくれることを知った。いずれ自分でも本をつくってみたい。いつからか、そんな気持ちを抱くようになった。
出版社を退職してからは、街ネタを取材するフリーランスのライターをしながら、週に一度は野毛のバーでアルバイトしていた成田さん。そのうちに、学生時代に出会った現在のパートナー星山健太郎さんが学業に区切りをつけることに。ならば、ふたりで一緒にできることを、と考えていた頃に偶然見つけたのが、現在星羊社がオフィスを構える伊勢ビルの物件。関内駅のすぐ近く、イセザキモールの入り口という好立地にある、丸窓が可愛らしいレトロビルだ。ただ、そのころは「ふたりで何かをやるなら、出版がしたい!」と漠然と考えていたものの、明確なビジョンはなかった。

「入居してみたら、伊勢ビルが1926年に建設された戦前からあるビルだとわかりました。歴史あるビルに事務所を置いたことで、自然とこの地域の歴史に興味を持つようになりました。だったら、横浜の今と昔を掘り下げながら酒が呑める雑誌を作るのはどうだろう、と考えたんです」(星山さん)
そう、星山さんと成田さんの強烈な共通点は「のんべえ」だということ。奇しくも、伊勢ビルは野毛まで徒歩数分という立地にある。2013年の初夏にオフィスを開設して半年後、12月には『はま太郎』がこの世に誕生した。

ただただ、野毛の下町的な雰囲気と、酒が好きだった
時間を少し巻き戻して、ふたりと野毛との出会いを紹介したい。星山さんは二十歳そこそこから酒好きで、大衆居酒屋に繰り出すのが日常だった。そこで耳にしたのが「横浜の中で最も面白い呑み屋街は野毛」という情報。横浜で生まれ育った星山さんは、すぐに野毛通いを始めた。
「その頃、若い人はあまりいなかったのですが、雰囲気が好きでよく通っていました。数年したら東横線の桜木町駅がなくなって、野毛が元気を失くしていく様子も目にしていました」(星山さん)
ほどなくして、星山さんと大学院の学友だった成田さんは、同級生らと連れ立って星山さんの案内で野毛を初めて訪れた。当初は知らない世界を探検するような気分だったが、同級生がひとり、ふたりと野毛通いに飽きていくなかで、最後まで残ったのが成田さんだった。
「酒の呑み方や酒場の面白さを教えてもらいました。店の趣味が合えば、常連さんとも話が合う。野毛ではみんな、はしご酒をするんですね。『次はどこ行くの?』と聞いたりして、それで次第に行く店が増えていって、知り合いも増えていく。そうすると、まちのことにだんだんと詳しくなってくるんです」(成田さん)
「野毛のお店は店主とお客さんの距離感が近いんです。最初はお酒を目当てに行っていたのですが、そのうち人に会いに行く感じになる。最初はそれがとても新鮮に感じました」(星山さん)
昔ながらの人との触れ合いがある酒場が集積する場所。人情味あふれる野毛を通じて意気投合した星山さんと成田さんは、その後、互いを人生のパートナーに選ぶわけだが、そんなふたりが、酒を酌み交わして、時間もお金もたっぷりと注ぎ込んできたこの場所をテーマに仕事をするのは自然な流れだった。

「市民酒場」を伝え続ける
現在は13号まで発刊されている『はま太郎』。創刊時から「市民酒場」の記事は、毎号欠かすことなく掲載してきた。市民酒場とは、昭和13年に結成された飲食店組合に加入している酒場のこと。なぜこうした市民酒場を媒体の軸に据えようと考えたのだろうか。そこには、野毛の常連客の間では3軒しか残っていないと言われた市民酒場が、実際はもっとたくさんあるという事実を知ったからだった。
「市民酒場ってなんだろう? ぐらいに思っていたら、西区にある大正時代創業の常盤木(ときわぎ)という店のマスターが、『まだまだある』と30店舗ほど名を連ねたリストを見せてくれて、組合を立ち上げたお店も教えてくれたんです。この事実を、自分たちが知っているのんべえのおじさんたちに教えてあげたら喜ぶだろうなぁと考えました」(成田さん)
「自分の知らない隠れた市民酒場がまだまだある。このワクワクを表現できたらいいなと」(星山さん)
市民酒場については現存する資料がほとんどなく、いままで調べたかぎりではほんの数行の記述しか見つからなかった。そこで、常盤木が持っていたリストを元に探偵のように話を聞いてまわり、その成果が『はま太郎』創刊号に掲載された。
「いろんな店に取材していくと、自分たちの中でも市民酒場に対する認識が変わっていったんです。成り立ちの経緯や戦後の変遷を知るにつけ、横浜の歴史が市民酒場を通じてまた違った視点で見えてくるようになってきました」(星山さん)
本にもインターネットにも掲載されていない歴史を、人づてに明らかにしていく面白さ。『はま太郎』制作の原動力はここにある。
外から見ていると、横浜はお洒落な港町。しかし、工場や港湾で汗を流して働いてきた労働者を癒してきた安価な赤提灯がいまもある。『はま太郎』を通じて触れる、素顔の横浜に好感をもつ人は多い。夜な夜な酒場歩きをする野毛ののんべえたちにも、綿密な取材がなされた『はま太郎』は新鮮に受け入れられた。
「桜木町の南改札を出てを出て左に行くとみなとみらい。右に行くと野毛なんです。横浜はあっち(左)じゃなくて、こっち(右)なんだよって、野毛の常連さんたちは店ではよくそういう話をするんです。こっちが好きな人は横浜のことが大好きなんだと。それを媒体にして見せたかった」(星山さん)

飛び込み営業で販売先を地道に開拓
創刊時はA5変形サイズでモノクロ、中綴じミシン製本とレトロ感漂うデザインが際立っていた『はま太郎』だが、11号からはA5無線綴じフルカラーにリニューアル。中小出版社向けの地方・小出版流通センターを通じて市場に乗せ、売り上げも徐々に増えてきた。
「取次と契約するときにはすごく悩みました。ネットでちょっと調べただけでは、本がどのように書店に流通するかわからなかった。でも、とにかくやってみるしかない、と契約に踏み切りました」(成田さん)
取次を通すだけではなく、書店との直取引も大事だと考えて営業を続けた。こちらも取次との契約同様、手探り状態でのスタートだった。アポなし営業OKという書店業界の独自ルールは知っていても、最初からうまく書店員とコミュニケーションが取れるわけではない。
「お店の方のお仕事の邪魔にならないよう気を遣っています。取り扱ってもらえそうな棚で作業している方は、大体その棚の担当者なので、声をかけさせてもらい、チラシや実物をお渡しして売り込みます。むやみに営業に行くわけではなく、お店の雰囲気に合っていて、しっかり扱っていただけそうな店に置いてもらうことが大事だと思っています」(星山さん)
そんな『はま太郎』も、横浜人にとっては馴染み深い老舗書店の「有隣堂 伊勢佐木町本店」とは創刊時からの付き合いだ。
「野毛で呑んでいたら、有隣堂の裏にある古書店の店主を酒場のマスターが紹介してくれたんです。お店を尋ねたら、当時の有隣堂の店長につないでくれて、ご近所(星羊社オフィスから有隣堂までは徒歩数分)だし、創刊号だしと置いてくれました。初めはご祝儀のような気持ちで購入してくれる方が多かったんですが、その後も謎の冊子が妙に売れると印象に残ったようで、それからずっと扱ってくれています」(星山さん)
地元愛の強い人が多い横浜だからこそ、地元密着型でなおかつ酒場という新鮮な切り口が快く受け入れられたのだろう。神奈川新聞と横浜市が共同編集する季刊誌『横濱』や横浜を特集した雑誌と並べて置いておくと、相乗効果でどちらもよく売れる。
このように信頼関係を築けている書店との直取引も上々で、現在は大阪、京都、高松など関西圏の書店も開拓し、13号の時点では33店舗と直取引を行っている。

宣伝も読者とのコミニケーションも、小さい出版社だからできるやり方で
40〜50代の男性をターゲットに、カウンターで酒を飲みながら読んでもらおうとつくりはじめたものの、意外なことに野毛でひとり呑みする女性たちにも支持されているという。続けてきて、読者の顔が見えるようになってきた。
「最初は星羊社がどういう会社かを知ってもらうため、名刺代わりにとにかく『はま太郎』を出し続けようと、隔月で10号までやり続けたんです。ただその時期は他のことがまったくできなくて」(星山さん)
ふたり体制の編集部で隔月発行の雑誌をつくり続けるのだから、それはもう毎日、目が回るほどの忙しさだった。現在は『はま太郎』を年に2回、ムック本や単行本を年に1冊とペースを定め、制作以外の時間を、読者とのイベントや営業、新規事業開拓にあてている。今年6月には、初の自主企画イベント「はま太郎フェス 旅と酒そして本」をさくらWORKS<関内>で開催し、約80名のファンで賑わった。もちろん厳選された酒が供される。
「出版社としても話題づくりをしていきたい。であれば、実際に読者と会う機会をつくって、雑誌をより身近な存在に感じてもらえたら。そして、イベントの後は一緒に乾杯したいなと」(成田さん)
イベントでは「ビブリオバトル」をもじり、酒好きのゲストが、自分がこよなく愛する酒場を語り、それを聞いた観客が最も行きたくなった酒場を選ぶ「知的バッカス合戦グビリオバトル」という名のゲームを独自に考案して開催。『はま太郎』の執筆者を含む4名のゲストが、5分で酒場の魅力を語りつくし、白熱したバトルになった。
「この6月には、鎌倉ブックカーニバルと、小田原ブックマーケットにも出店しました。そのときのためだけに表紙を木版で手刷したイベント限定の冊子もつくりました。小さな出版社だからこそ小回りの効いた仕掛けをいろいろ試したい」(星山さん)
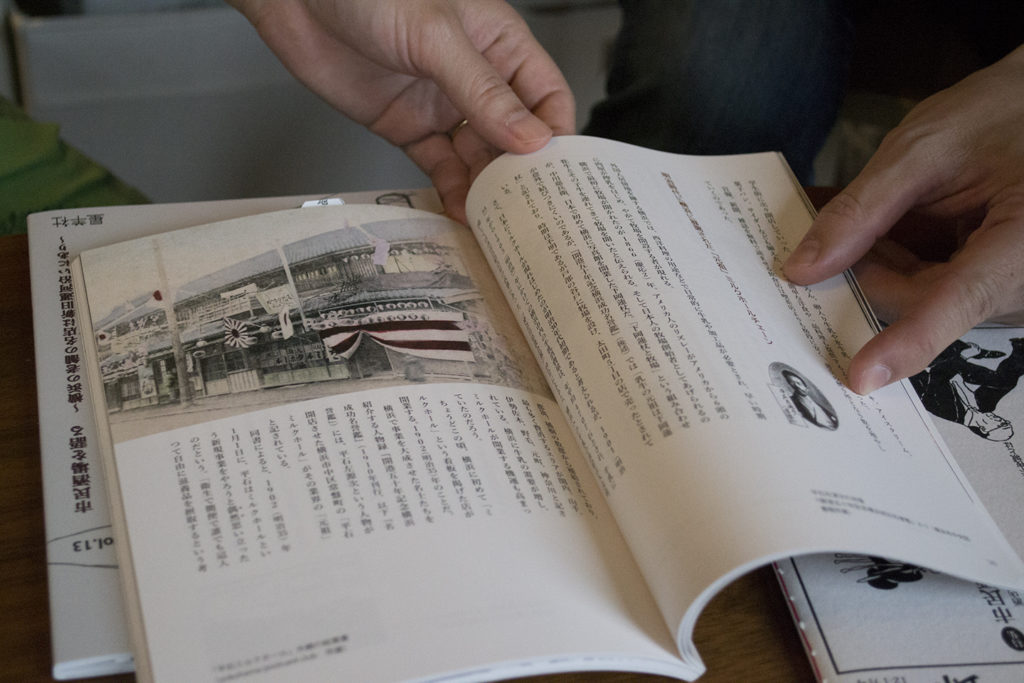
実は星羊社、出版社ではあるがホームページのショップでは各種グッズや雑貨が充実している。オリジナルの「珠玉の酒肴カレンダー」や「Bar YOKOHAMA」コースター、手ぬぐいなどは、デザイン担当の成田さんが手がける。アイデアを思いついたらすぐにかたちにする、そんなスピード感が星羊社の魅力だ。
横浜から全国へ。星羊社のこれから
ここ最近、昭和の香りが色濃く残る大衆演劇の劇場「三吉演芸場」や、下町風情の横浜橋商店街がある横浜市南区に引っ越したふたり。それに伴って、『はま太郎』も野毛界隈だけでなく、南区の話題も取り扱うようになった。
「下町に面白みを感じるんですね。家から一番近い大正創業の昔ながらの酒屋さんは角打ちがあって、八十代のお母さんが昔、横浜にミルクホールがあった頃の話を教えてくれたりするんです」(星山さん)
近所に行きつけの店ができれば、店主と仲良くなって昔の話や写真を提供してもらえるので、自然とネタが溜まっていく。「仲良くなってから聞かせてもらう情報は質が違う」と星山さんたちは口を揃える。
「取材の申し込みは、無理をしないと決めています。もちろん、取材を承諾いただいたら、原稿確認は慎重にやります。一度、店主のお名前を間違えてしまった時は、羊羹を持って謝りに行きました。小さいメディアだからこそ取材に応じてくれるお店は少なからずあるので、その気持ちには誠実に応えたい」(成田さん)
取材先との関係性は、あくまで等身大。『はま太郎』のコンセプトは一貫している。今後の展開について聞いてみた。
「いまは横浜に限定していますが、たとえば、徳利をテーマに全国を取材対象にしてもいいかもしれません。店のロゴが入っている徳利を使っているところはいいお店が多い、なんていう持論を検証するなんてどうだろう。どうせやるんだったら、遊び心が欲しいですね」(星山さん)
『はま太郎』は、地元の酒呑みだけでなく、全国の小規模出版に携わる同業者にもファンが多い。設立から現在まで、横浜と酒をテーマに突き進んできたふたりの情熱には舌を巻くが、『はま太郎』らしさを残したまま、横浜から全国へ飛び出していった時に、どんな本が生まれるかにも注目したい。
